オンライン診療ガイドライン【御散歩雑談】20180525
定期的に病院に通っているが、予約しているにも関わらず、大抵は1時間待つ。一人一人の対応時間が読めない面もあるだろうが、先生の回診の都合や病院経営のために1時間あたりの患者数が割り当てられ、詰め込まれているのだろうと推測できる。
でも、先生と話す内容としては、体重を計り、血圧を計り、自分の体調がどうか、記録された血液の値の問題点、その対処、処方する薬が変更ないこと、日常生活で気になっていることの相談、そして次回の予約。
オンラインでTV会議でできそうな気がしていた。
厚生労働省からガイドラインが通知され、オンライン診療が進みそうではある。ガイドラインを参考に実際に”やる”となった場合に気になる部分を列記してみる。
- 対象となる患者の症状が安定していること
同意できる。
- 患者側の求めがあった場合に限って実施する
患者が言わないとやってくれないのではなく、医師からの提案が必要ではないか
- 最初の診療は原則対面
同意できる。
- オンラインでは触診などを行えないリスクを事前に説明
当然。
- 症状が急変した場合に備えた計画を立てる
当然。
- 診療は原則、同じ医師が対応し、オンラインと併せて定期的に対面診療も行う。
現在の主治医がオンライン対応しない場合は、担当医が変わってしまうのではないか。
- オンラインが適切でないと判断した場合、速やかに対面に切り替える。
当然。
- 複数患者の同時診療は禁止した。
これをやらないと効率化されない。
- 情報漏えいや改ざんがないよう、使用する情報機器などのセキュリティー対策を医師に求めた。
このハードルは高い。そういう知識のない医師はやらなそうだ。大手病院、オンラインを中心にした医療機関でないと技術者を雇えないのではないか。
- オンライン診療時に医師がいる場所は、医療機関である必要はないが、情報保護などの観点から公衆の場は不可
同意。カフェからやる人が出てくることを想定?
血液検査や尿検査
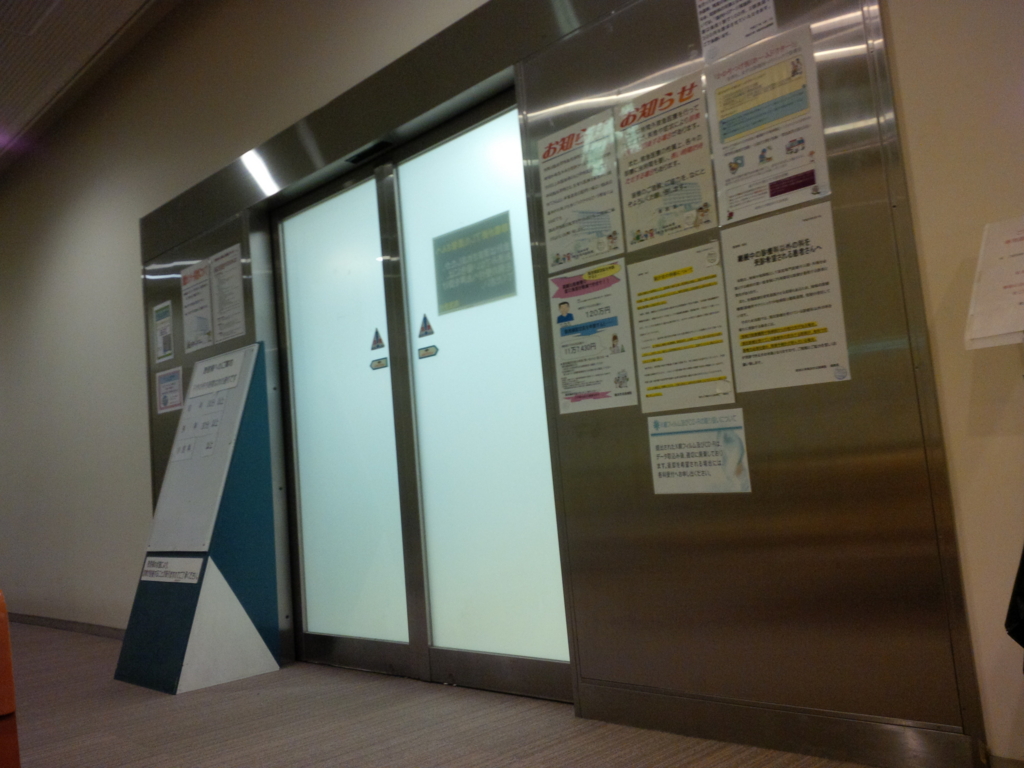
は、近くのクリニックで行い結果を主治医とシェアできるようにする必要がある。
セキュリティ対策は当然だが、多くの先生はそんなことに自分の知恵や予算を裂こうと思わないだろう。結果として大手病院や大学病院しかできなさそうだ。地域の開業医院でもやる人がでてくるといいが。。
また、患者からの申し出という縛りは、申し出をしやすくするという対策を講じないと、誰も申し出ないあるいは申し出は少ないということになるのではないか?
こういう積極的なクリニックが多数登場してほしい。