【ODRピックアップ/半蔵門ビジネストーク】20161117 何科へいきますか?
最近はそうでもないのかもしれませんが、一時期、病院に行って、診察を受けようとするときに、最初に通される初診受付的なカウンターで、アンケート的な問診に応えた後、
「何科にかかりますか?」
と聞かれることがよくありました。
最初は、風邪ぽいので内科でしょうか?とか、マジメに応えていましたが、ある時にキレました。
「それが分からないからここにきて、アンケートしたんじゃないの?今のヒアリングで何科にいくべきかわからないの?」
すると、
「そうですね。胃のあたりなら、消化器科、腎臓や肝臓ならそちらの科です」
「だからその判断は素人にはわからないでしょう?だから聞いているのに。。」と押し問答。
「でも、最初に消化器科にかかられて、もし原因が違えば、また別の科で順番待ちをしていただくことになりますが。。。」と、待ち時間を考えてのことのようなのですが、本質とずれてしまっています。正確に診断をしてもらう方が重要です。それとも、待ち時間に拘る人が多いのか。。。
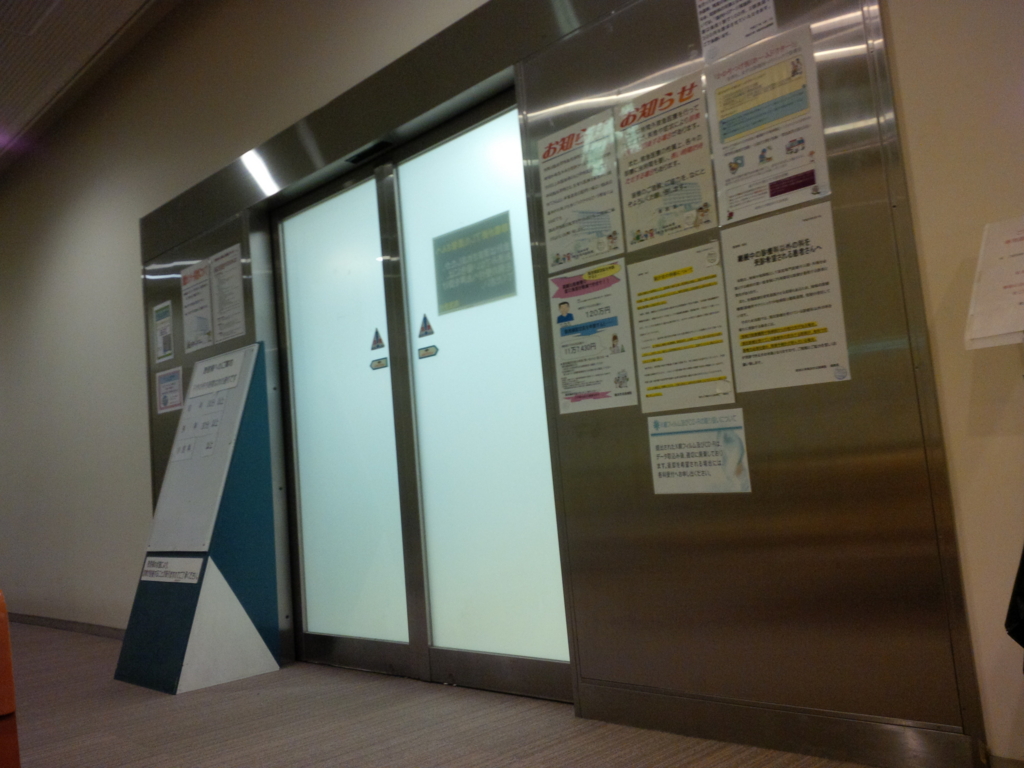
* * *
最近かかった医院の先生は頼りになりました。
「XXだと思うのですが。。。」
症状をいろいろ聞かれます。
「熱は?」
最初に症状が出た日に、38度でました。
「なるほど。」
「これは、XXではありませんね。まず男性はなりにくい。それから発熱。これも連動しません。別の原因がありそうです。ZZとかね。ZZは、XXと症状が似てくるのです。血液検査、来週エコー検査をやりましょう。今日は、ZZを想定した症状の改善に効果のある抗生剤を出しておきます」
これですよ。お医者さんに期待したいのは。
思い込みとネット知識で推測した病名を、ある症状との複合性から、違うと判断して、本来の可能性にたどり着く専門知識。TVドラマで、この傾向のがあり大好きです。米国だと、ドクターハウス。日本だと、踊るドクター(主演:東山紀之)、レディダヴィンチ(主演:吉田羊)。ドラマになるのは、実際には難しいし、そうしたドクターも少ないからだと思いますが。。。
* * *
そして、AI。
こういうのが人工知能でできそうです。
論文を読み込み、それらを学習し、ある種の判断を下すことができるそうですが、前述の先生の見立ての論理からすれば、十分出来そうなことです。
人間って、人間に厳しくて、見立てを人間の誰かがやって、結果間違うと、「プロとしてどうよ!」って、怒るけど、AIと解っていて、初期診断されればありがたがるし、結果違っていても、「やはり人間の先生に見てもらってよかった」と、先生感謝の気持ちで終わると思いますので、早いとこ実用化を望みます。